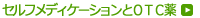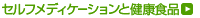第4回「効きそうな食品」の中身(2)いわゆる健康食品
2005年08月01日
日本の食品分類の中に「いわゆる健康食品」があります。これは野菜や魚などとともに一般食品に分類されています。中身は実にさまざまで、健康食品、サプリメント、栄養補助食品、ダイエット補助食品等々の名称で呼ばれていますが、いずれも定義や決まりがあるわけではありません。ですから、公的な文書などで用いるときにはストレートに健康食品とは言わずに、いわゆる健康食品あるいは「健康食品」などと表します。
いずれにしてもこれらの食品群は、ヒトの体への何らかの効果を期待して用いられる「効きそうな食品」というわけです。効きそうな食品をじょうずに取り入れて体調を管理したいものですが、商品の種類も中身もさまざまですから、まず、いいものを選ぶための知識が必要となります。
健康を維持するための食品としては、「安全であること」と「食品の目的に合ったものであること」が最低限の条件といえます。
◆食品が安全であるとは…
・使われる素材に長い食経験があり、有害性がないこと
・有効とされる成分が多すぎず、不純物は少なく、衛生的に造られていること
・医薬品や不法薬物などを含んでいないこと
◆食品の目的に合ったものとは・・・食品の三つのはたらきを持つ
1.生命を維持し、健康を保持する・・・栄養素の補給
2.味や香りなどを楽しむ・・・嗜好を満たす
3.からだの調子を保つ・・・生体の機能調節
「健康食品」を取るとき、以上の点を満たしているかどうかを見ると良いでしょう。とは言っても、きちんとした基準、試験、表示などの情報がなければ、これは大変むつかしいことです。そして残念ながら、現在出回っている“いわゆる健康食品”には次のような問題点があるのです。
*品質、安全性の保証があるものは少ない
*ヒトが食べたときの効果が証明されていない
*濃縮型の形態のもの(錠剤、カプセルなど)は過剰摂取の危険性がある
*アレルギー、副作用などの情報がない
*病気や服用薬への影響があるものがある
*経済的負担が大きい
![]() 日本の食品制度の中で、ヒトでの効果と安全性が科学的に確かめられ、効果の表示が認められているのは、保健機能食品(特定保健用食品)だけです。最近、審査の条件が少し緩和された「条件付特定保健用食品」も出はじめました。 右のマークが目印です。次回から問題点を少し詳しく見ていきましょう。
日本の食品制度の中で、ヒトでの効果と安全性が科学的に確かめられ、効果の表示が認められているのは、保健機能食品(特定保健用食品)だけです。最近、審査の条件が少し緩和された「条件付特定保健用食品」も出はじめました。 右のマークが目印です。次回から問題点を少し詳しく見ていきましょう。